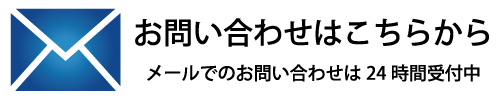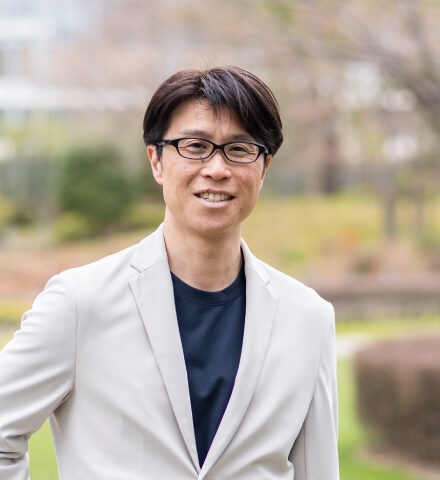借地権付き建物の売買・売却・譲渡を進めるうえでの注意点
親からの相続の手続きをしているときなどに、相続財産の中に借地権付き建物があることが分かる場合があります。
借地権付き建物とは、土地を誰かから借り、その土地に建物を建てることを指しており、土地と建物の所有者が異なります。
このようなケースで借地権付き建物を売買したり、売却・譲渡したりすることはできるのでしょうか。
借地権付き建物の売買・売却・譲渡の注意点

借地権付き建物は建物自体とその建物が立っている地主が異なるため、通常の建物の売買に比べて多くの注意点があります。
では借地権付き建物の売買・売却・譲渡を行う際に留意すべき注意点について見ていきましょう。
借地権の種類に注意する
借地権付き建物の売買・売却・譲渡を考える場合に、まず考慮すべきなのは借地権の種類です。
借地権という権利は古くから存在しており、借地権について定めた法律も改正されています。
そのため今設定されている借地権がどのような内容なのかを把握しなければならないのです。
借地権には古いものを含めて5つの種類があるので一つずつ見ていきましょう。
まず「旧借地権」と呼ばれる借地権があります。
これは1992年8月より前に借りた土地に適用されているもので、借地権の存続期間と最低期間とが定められています。
もし借地権付き建物が木造である場合、存続期間は30年、最低期間は20年以上、更新後の期間は20年以上です。
一方建物が鉄筋造もしくは鉄筋コンクリート造である場合、存続期間と最低期間は60年、更新後の期間は30年と決められています。
このように建物のつくりによって異なる存続期間や更新後の期間が設定されているのが旧借地権の大きな特徴です。
一方で1992年8月以降に借りた土地に適用されるのが、「普通借地権」です。
普通借地権は旧借地権とは異なり、建物の構造による存続期間や最低期間の違いはありません。
どのような建物であっても、存続期間は30年、1回目の更新期間は最高で20年以上、それ以後は最高10年以上を定め更新することができます。
普通借地権の更新は地主ではなく借地人の意思が優先されます。
特別な理由がない限り、借地人が更新の意思を示せば借地権の更新が可能です。
この2つに加えて、借地権を設定する契約期間を定めるのが「一般定期借地権」です。
一般定期借地権は長期にわたってある土地を利用することを前提としているもので、最低期間が50年に設定されています。
ただし定期借地権の契約を交わした場合、基本的に更新はなく、契約期間満了後は該当する土地を更地にして返却しなければなりません。
借地権付き建物に永久に住む予定がない、子や孫に相続させるつもりがないといったケースでは一般定期借地権を設定するのがよいかもしれません。
定期借地権の中でもとくに店舗などに利用するためのものを「事業用定期借地権」と呼びます。
住宅用の定期借地権と同様、契約期間が定められており契約の更新はありません。
契約終了後は土地を更地にして所有者に返却する必要があります。
事業用定期借地権の大きな特徴は契約期間が住宅用の定期借地権よりも短くなっているという点です。
そのためコンビニなど一時的に店舗を構えるといったケースで利用されることの多い借地権です。
住宅用の定期借地権が最低期間50年であったのに対し、事業用定期借地権の場合には10年以上50年未満の範囲で設定可能です。
5つ目の借地権は「建物譲渡特約付借地権」です。
通常借地権は契約終了後土地を更地にして所有者に返却しなければなりません。
しかし建物譲渡特約付借地権の場合、建物を地主が買い取ることになります。
借地権の契約後30年以上が経過したときに地主が建物を買い取り、借地権が消滅します。
土地を借りている側からすれば建物の解体費用が浮く、地主からすれば建物が手に入るといったメリットがある方法です。
売買・売却・譲渡に際しては地主の同意が必要となる

借地権付き建物の売買・売却・譲渡では、借地権の種類に加えて地主の同意が必要となります。
建物の所有者が、自分の所有物である建物を売るのだから地主の同意など必要ないと感じるかもしれませんが、実はそうではありません。
なぜなら、借地権付き建物を売却する場合には、建物の所有権と借地権を一緒に移転させなければならないからです。
そして借地権を移転するためには、地主の同意が必要です。
借地権は地主と利用者との信頼関係が非常に重要です。
さらに借地権の契約は通常数十年単位の期間に及ぶ契約であるため、地主が借地権の移転に同意しないことも決して珍しくありません。
地主の中には特定の借地権者だから契約をしていると感じている方もいます。
もし新たな契約者が土地をきちんと管理してくれなかったり、賃料を支払ってくれなかったり、最初に交わした契約内容を履行してくれなかったりすれば、被害を受けるのは地主です。
したがって借地権付き建物の売却は建物の所有者の独断では行えず、地主の同意を得なければならないのです。
契約更新の際の更新料について買主に説明する
無事に地主の同意が得られたとしても、借地権付き建物の売買・売却・譲渡には別の注意点もあります。
それは更新料について買主に説明しておかなければならないという点です。
借地権は旧借地権であれ普通借地権であれ、契約期間が定められています。
契約期間が終了すれば、契約を更新するか終了するかを借地人が決めなければなりません。
契約を終了する場合には建物を取り壊して土地を所有者に返却しなければならず、契約を更新する場合には基本的に更新料を支払う必要があります。
とくに1992年8月以降に契約した場合には1回目の更新が20年、2回目以降の更新は存続期間が10年と短く設定されています。
さらに借地権の更新料は土地の価格を基準に算出されるので、場合によっては数十万円、数百万円かかるケースも珍しくありません。
そのためどのくらいの更新料がかかるのかについて買主に説明しておくのは親切なことです。
買主としても、借地権付き建物を購入した数年後に数十万円、あるいは数百万円の更新料がかかることを知ったうえで契約するか検討したいと思うことでしょう。
あとでトラブルになるのを防ぐためにも、更新料をいつ、どのくらい支払う必要があるか説明して契約することが重要です。
借地権付き建物を相続する場合の注意点
借地権付き建物を売却する場合、借地権の種類などに注意しなければなりませんが、相続でも注意すべき点があります。
相続人が一人しかいない場合、それほど大きな問題は生じないかもしれません。
相続人が被相続人から借地権付き建物を相続し、そのまま収益を継続して得ればよいからです。
しかし相続人が複数いるケースでは注意が必要です。
というのも、複数人の相続人が借地権付き建物を相続して、かつ収益を継続して得られない場合には、通常不動産を換金して得た現金を相続人で分けることになるからです。
しかし借地権付き建物は前述のようにすぐに売却できるとは限りません。
地主の同意が得られないかもしれませんし、買い手が見つからないかもしれません。
相続の手続きが進んでいない間も、地代の支払いは継続しなければならないでしょう。
借地権付き建物の相続に伴う手続きは煩雑になる恐れがあるので、もし近い将来相続が発生しそうなのであれば、できるだけ早く売却もしくは譲渡の計画を立てて手続きを進めておくことは必要となるでしょう。
そもそも借地権付き建物の売買・売却・譲渡は可能か

このように借地権付き建物の売買・売却・譲渡にはいろいろな注意点がありますが、そもそも借地権付き建物を売却したり譲渡したりすることは可能なのでしょうか。
借地権付き建物の売買・売却・譲渡は可能
結論からいえば、借地権付き建物を売買したり、売却・譲渡したりすることは可能です。
確かに地主と建物の所有者は異なりますが、自分の所有物である建物を売却したり譲渡したりするのは所有者の権利です。
ただし前述の通り、借地権付き建物を売却・譲渡する場合には地主の同意が必要となります。
借地権付き建物の売買には借地権の移転が関係してくるので、必ず地主とコミュニケーションを取って手続きを進めていくようにしましょう。
トラブルを防ぐためにも密なコミュニケーションは重要です。
借地権付き建物の売買・売却・譲渡の方法

では無事に地主から同意が得られた場合、どのように借地権付き建物の売買・売却・譲渡を行えばよいのでしょうか。
借地権付き建物の売買にはいくつかの方法があるので、どのような方法を利用するかを慎重に検討しなければなりません。
まず考えられるのは、地主に買い取ってもらうという方法です。
すでにそれを織り込んだ建物譲渡特約付借地権を設定する場合もありますが、そうでなくても地主に建物を買い取ってもらうことは可能です。
借地権についてはすでに地主から買っているため、建物も一緒に売却することができれば手続きもスムーズに進みます。
もし地主に借地権付き建物を売却するのであれば、2つの方法から都合のよい方を選ぶことができます。
1つ目は、借地権と建物を両方買い取ってもらう方法です。
借地権と建物を両方売却するのであれば、より高値で自分の所有物を売ることができるでしょう。
さらに地主との信頼関係がある程度築かれているので、お互いそれほど不安を抱かずに売買契約が結べるのもメリットといえるかもしれません。
2つ目の方法は建物を取り壊して借地権だけを売却するという方法です。
こちらは建物の解体費用がかかるうえ、借地権だけを売却することになるので得られるお金が少なくなります。
ただ地主としては借地権を購入した後すぐに土地を再利用できるので契約がスムーズに行えるかもしれません。
しかし、先に建物を壊してしまう場合にはトラブルになるケースもあります。
以前、地主が更地にしたら借地権を買い取るという約束を口頭でしていました。建物を解体したのちに地主が借地権を買わないと言われてしまった。
弊社に相談があった事例ですが、こうなってしまった場合、弁護士を立てて交渉するしかありません。
こういった事を未然に防ぐためには、口約束で話を進めるのではなく、必ず書面にて残し建物を解体するようにしましょう。
借地権付き建物の売買の別の方法は、地主以外の第三者に売るというものです。
地主の承諾が得られた場合、借地権の価値の1割程度を承諾料として地主に支払うのが一般的です。
こうした出費についても考慮しながら第三者に売却するかどうかを決定するとよいでしょう。
ほとんどが仲介業者に借地権付き建物の買い手を探してもらうという方法になると思います。
これは自分で買い手を見つける時間やノウハウがないという方におすすめの方法です。
もちろん自分で買主を見つけることも可能ですが、地主さんとの交渉などが絡むため借地権に精通した不動産会社に依頼をしたほうがいいと思います。
仲介業者であれば、借地権付き建物を探している買い手の情報を多く持っているはずです。
借地権付き建物の売買は金額が大きくなるので、個人で契約するのは怖いと感じている方の場合にも、仲介業者に依頼すれば問題なく契約が結べるでしょう。
ただし借地権付き建物の売買に詳しい業者を選ばなければならないこと、仲介手数料を支払わなければならないことに留意しましょう。
仲介業者と似ていますが、買取業者に買い取りを依頼するという方法もあります。
仲介業者が売り手と買い手の橋渡し役になるのに対し、買取業者は買主として直接借地権を購入します。
借地権付き建物を売りたい人にとっては、すぐに建物の売却ができるという大きなメリットがあります。
仲介業者に依頼しても買い手が見つかる保証はないので、買取業者に売ってしまった方がよいと感じる方は少なくありません。
買取業者であれば買主の立場として地主との折衝も行ってくれるので、とても便利です。また、直接の買主なので地主との交渉も一歩踏み込んで交渉ができるのも大きなメリットの一つです。
ただし買取業者に借地権付き建物を売却する場合には、価格が思ったよりも安くなってしまうことがあるので注意しましょう。
しかし、買取業者が買主となる場合、契約不適合責任(旧、瑕疵担保責任)を免責してくれたり、本来売主負担で行わなければならない測量、建物解体(建物が古い場合)、残置物の撤去など含めて買主業者の方で負担してくれたりします。
借地権付き建物の売買・売却・譲渡のメリット

借地権付き建物を売買・売却・譲渡することにはいくつかのメリットがあります。
もしこれから借地権付き建物の売買を考えているのであれば、ぜひメリットについて知っておくようにしましょう。
価格が安い
借地権付き建物を購入する方のメリットとなるのは、価格の安さです。
借地権付き建物の場合、購入代金に土地の代金は含まれていません。
そのため建物と借地権の値段となるため、通常の土地付き家屋を購入するよりもかなり安くマイホームを手に入れることができるでしょう。
一般的に借地権の価格は土地の価格の60%から80%程度とされています。
とくに都心部にマイホームを欲しいと考えている方の場合、土地代だけで非常に高額になってしまうかもしれません。
しかし借地権付き建物であれば、余裕をもって購入できるという方もいるでしょう。
もし思ったよりも安くマイホームが手に入るのであれば、浮いたお金を使ってリフォームしたりこだわりの庭を作ったりすることができるのです。
購入費用が安いということはローンが組みやすいということでもあります。
土地建物をすべて購入するためのローンは組めなくても、借地権付き建物を購入する金額であればローンの審査が通るという可能性もあるでしょう。
土地部分の税金を支払わなくてもよい
不動産の所有者にとって、税金は悩みの種です。
土地を所有しているのであれば、毎年固定資産税を払わなければなりません。
しかし借地権付き建物を購入すれば、土地部分の固定資産税を支払う必要はありません。
不動産についてはその所有者が税金を払わなければならないためです。
したがって建物の固定資産税等は購入者が支払わなければなりませんが、土地の固定資産税や都市計画税は支払う必要がないのです。
借地権付き建物を購入した場合、初期費用が少なくて済み、かつランニングコストも抑えられるのです。
土地を半永久的に使用できる
借地権付き建物を売買する別のメリットは、その土地を半永久的に使用し続けられるという点です。
借地権は旧借地権の場合建物の構造によって30年もしくは60年、普通借地権は30年、定期借地権は50年と存続期間や最低期間が定められています。
その後は地主と借地権者との間の合意によって契約を更新することが可能です。
しかし実際には借地権者が更新の意思を示せば、基本的に地主はこれを拒否することはできません。
もちろん建物が老朽化して危険であったり、借地権者が著しい契約違反を犯したりしているような場合は別です。
したがって借地権者が契約更新の意思を示している限り、その土地を半永久的に使用し続けられるということになるのです。
もし借地権付き建物を相続したり、譲渡したりする場合でも、相続人がその土地を半永久的に使い続けられるのは大きなメリットといえるでしょう。
借地権付き建物の売買・売却・譲渡の流れ

借地権付き建物を売買・売却・譲渡する場合には、その手続きの流れについても知っておくことが重要です。
では借地権付き建物の売却・譲渡の流れについて見ていきましょう。
地主に売却するケース
まず地主に借地権付き建物を売却するケースについて考えます。
地主とよい関係が築けていたとしても、まずは不動産会社に相談しましょう。
地主は、当然ですが借地権を安く買い戻したいと思っています。
一方で借地権者はできるだけ借地権や建物を高く売りたいと思うはずです。
両社の利害関係は対立しているため、交渉をスムーズに進めるためには不動産会社や仲介業者の助けが必要なのです。
地主に借地権や建物の購入意思があることが確認できたなら、契約の条件について話し合うことができます。
この交渉も不動産会社などの第三者を交えて行う方が望ましいでしょう。
交渉でとくに重要なポイントは、売却価格、売却時期、そして引き渡し方です。
地主が建物も併せて買い取るのか、借地権者が取り壊して更地にするのか、取り壊しの費用はどちらが負担するのかなどについてもしっかり話し合うようにしましょう。
条件が決まれば、あとは契約を締結して決済・物件の引き渡しへと進みます。
もちろん建物の所有権移転登記なども行わなければなりません。
第三者に売却するケース
もし地主以外の第三者に借地権付き建物を売却するのであれば、売却の流れが少し異なります。
最初に不動産会社に相談してから、地主の承諾を得なければなりません。
地主から売却の承諾を得るのは難しい場合もあります。
とくに借地権付き建物の買い手が建物の建て替えを希望している場合や、住宅ローンの利用を検討している場合などはその承諾も得得なければなりません。
したがって根気強く地主と交渉することが必要になるでしょう。
さらに地主が借地権付き建物の売却に同意した場合、借地権者は承諾料を地主に支払うのが一般的です。
通常借地権の価値の1割程度ですが、これも交渉しなければならないでしょう。
地主が借地権付き建物の売却に同意したなら、不動産会社に買い手を見つけてもらいます。
買い手が見つかれば、あとは売買契約を締結して地主から譲渡承諾書を受け取り、決済・物件の引き渡しへと進みます。
地主が借地権付き建物の売却に同意しない場合

借地権付き建物の売却には、地主の同意が必須です。
しかし場合によっては、地主がどうしても借地権付き建物の売却に同意しないことがあります。
理由はさまざまですが、借地権者が変わるのが嫌だったり、できるだけ安く借地権付き建物を購入しようとしていたりするかもしれません。
しかし地主の同意が得られなければ建物が売却できないのであれば、建物の所有者や相続人は困ってしまいます。
そんなときに利用できるのが「土地賃借権譲渡許可の申し立て」です。
土地賃借権譲渡許可の申し立てとは、借地権付き建物の売却を裁判所に許可してもらう手続きのことです。
裁判所は借地権の譲渡を認めても地主が不利益を被らないかどうかを調査し、借地権付き建物の売却を許可します。
もちろん、買い手が社会的に著しく信用がなかったり、騒音や振動を伴う事業を計画したりしている場合には許可が下りない場合もあります。
地主からすると、自分が同意していないのに裁判所が借地権付き建物の売却を許可することに不満を感じるかもしれません。
そのため土地賃借権譲渡許可の申し立てが認められた場合には、地主に借地権付き建物を優先的に買い取る権利が与えられます。
地主に建物を買い取る意思がない場合には、借地権者は第三者に借地権付き建物を売却することができるのです。
借地権付き建物を売却する際にかかる費用
借地権付き建物を売却する際には、かなりの費用がかかることも珍しくありません。
実際に売却するときに驚かないためにも、どのような費用が生じ得るのか知っておくようにしましょう。
まず考えられるのは建物の取り壊し費用です。
地主や第三者が建物も併せて買い取ってくれるケースを別にすれば、土地を更地にして引き渡さなければなりません。
その場合には建物の取り壊し費用が発生します。
そして建物の取り壊し費用は基本的に借地権者が負担することになります。
あくまで目安ですが、木造住宅では1平方メートルあたり15,000円前後の解体費用がかかります。
家の大きさにもよりますが、数百万円の費用がかかると考えておくべきでしょう。
続いて地主への承諾料が必要です。
これは借地権の価値の1割程度です。
さらに該当する土地の境界がはっきりしていないこともあるかもしれません。
その場合には測量して正確な境界を定め、正確な面積を算出する必要があります。
この測量費用も基本的には借地権者が支払うことになるでしょう。
加えて仲介業者を利用する場合には、仲介手数料がかかります。
仲介手数料は宅地建物取引業法で上限が決められています。
仲介業者を利用する場合には、必ず契約書をチェックして仲介手数料が法律で定められている範囲内かを確認してください。
こうした費用に加えて売買契約書に貼る印紙代、売却した際の利益に課税される譲渡所得税についても考えておく必要があります。
借地権付き建物の売買・売却・譲渡の成功ポイント

借地権付き建物の売買・売却・譲渡には様々な手続きやステップがあることが分かりました。
ではどうすればスムーズに借地権付き建物の売却を進めることができるのでしょうか。
借地権付き建物の売買・売却・譲渡の成功ポイントをいくつかご紹介します。
地主とのコミュニケーション
借地権付き建物の売買・売却・譲渡を成功させる最大のポイントといえるのは、地主とのよいコミュニケーションです。
借地権付き建物を地主に売却するにも第三者に売却するにも、地主の承諾が必要となります。
地主とよい関係か築けていると、売却交渉もスムーズに進めることができます。
さらに買い手がその土地に住み始めても、地主とトラブルになるリスクを最小限に抑えられるでしょう。
借地権付き建物の売却を考えているのであれば、今から地主との関係をよいものにするよう努力するべきです。
可能な限り低価格での売却を考える
続いての成功のポイントは、売却価格についてです。
借地権付き建物を売る際には、当然できるだけ高く売りたいと願うものです。
そのため不動産会社が査定した最高額で売却活動をする方が少なくありません。
しかし借地権付き建物の売却を成功させるためには査定額よりも安い価格設定にすることがコツです。
というのも、借地権付き建物はそもそも買い手が付きにくい物件だからです。
借地権付き建物は購入したあとさらに建て替える必要があるかもしれません。
さらに購入後も引き続き地代の支払いが必要です。
もし借地権の契約更新があれば、数十万円や数百万円単位の更新料を支払うことになります。
そのため査定額よりも安い価格設定でなければ、買い手としても魅力を感じにくいのです。
借地権の更新料や地代の支払いを考慮すれば、少し無理をしてでも土地と建物両方を買った方がよいと判断する人もいるでしょう。
借地権付き建物の売却においては、価格設定に十分注意が必要なのです。
借地権付き建物の取り扱い実績のある仲介業者や不動産会社を選ぶ
借地権付き建物は不動産の中でも取り扱いにくい物件の一つです。
そのため取り扱い経験の少ない仲介業者や不動産会社に物件の相談をすると、あまり良い結果になりません。
不動産会社からすると、借地権付き建物は売り手や買い手に加えて地主とも交渉しなければならない難しい案件となります。
それにもかかわらず売却の利益は少ないので、あまりうまみのない物件になってしまうのです。
借地権についての知識や経験のない仲介業者や不動産業者では買い手がまったく見つからなかったり、売り手に不利な条件で売却せざるを得なくなってしまったりするかもしれません。
さらに得られる利益が少ないからという理由で、不動産会社が販売活動の手を抜いてしまう事も考えられます。
一方借地権付き建物を数多く取り扱っている業者であれば、地主への承諾料をできるだけ抑え、売却の価格をできるだけ高くすることができます。
しかも法律の面でも借地権についてよく理解している業者ならば、契約時のトラブルも起こりにくいでしょう。
借地権付き建物の売却が成功するかどうかは、不動産会社や仲介業者選びにかかっているといっても過言ではありません。
【まとめ】
借地権付き建物の売買・売却・譲渡は慎重に進めよう
借地権付き建物の売買・売却・譲渡にはさまざまな要素が関係しています。
地主との交渉や、値段交渉、発生する費用の分担など考慮すべき点が多くあるからです。
個人で交渉するよりも、仲介業者や不動産業者などに交渉・手続きを依頼した方がストレスなく売却・譲渡を進めることができるかもしれません。
契約でトラブルが起こらないよう、コミュニケーションを欠かさず慎重に手続きを進めるようにしましょう。