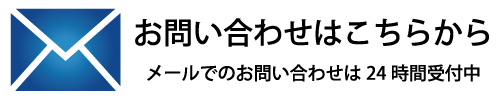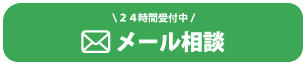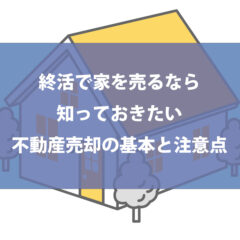借地権とは? 旧借地法と新借地借家法を徹底比較し、相続・売却・地主交渉のポイントまで解説
借地権とは何か
借地権とは、他人の土地を借りて、自分の建物を所有するための権利です。
一般的に「地上権」あるいは「土地の賃借権」として設定されることが多く、借地人は地主に地代を払いながら土地を利用し、建物を長期的に所有することが可能です。
地上権
物権であり、登記による対抗力が強い。
一度設定されると、地主が変わっても原則的にそのまま継続可能。
賃借権
契約(賃貸借)による債権的権利。第三者に対しては建物の登記などが対抗要件となるため、契約書に加えて建物登記の有無が重要になる。
借地権は、土地を購入するより初期費用が抑えられる利点がある一方、地代を支払い続ける必要や建物の改築・売却時に地主の承諾が必要になるなど、特有のルールがあります。
図表:借地権に関する概要
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 定義 | 他人所有の土地を借りて建物を所有する権利(地上権または賃借権) |
| 主な法律 | 旧借地法、新借地借家法(平成3年) |
| メリット | 土地購入費不要、相続税評価が低めなど |
| デメリット | 地代、承諾料が発生、担保評価が低く融資が受けにくいことも |
| 注意点 | 地主との関係、契約更新、増改築・売却時の承諾など |
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中
旧借地法で定める借地権の特徴
かつては、大正10年制定の「借地法(旧借地法)」が借地に関する主要な法律として存在していました。
1992年(平成4年)の新借地借家法(平成3年法律第90号)施行に伴い旧借地法は廃止されましたが、経過措置により旧法契約がそのまま継続されるケースが現在でも多く残っています。
旧借地法の法的根拠とよくある勘違い
旧借地法には、例えば以下のような条文が存在します(条文番号は旧借地法のもの)。
第1条「本法において借地権と称するは…」
第2条「借地権の存続期間…」
第4条「借地権消滅の場合において…建物買取請求…」
よくある勘違いとして、「旧借地法はすでに廃止されたから全て新法に切り替わっている」と勘違いされている方もいますが、実際には経過措置により、旧法のまま長期継続する契約が広く存在しています。
地主としても、借地人が旧法適用だと地代の値上げや契約終了が難しい、という事実があるため、双方のメリット・デメリットを再検討する際には専門家立ち合いで話し合うことが望ましいでしょう。
存続期間と更新ルール
| 存続期間(旧借地法第2条) | |
|---|---|
| 堅固建物(鉄筋コンクリート造、鉄骨造など) | 60年 |
| 木造など非堅固建物 | 30年 |
| 契約更新 | 借地人が土地を引き続き使用していれば、地主が更新拒絶することは極めて難しい仕組みです。 旧借地法下では、地主に「正当事由」がなければ更新拒否ができません。 |
借地人保護の代表例・建物買取請求
旧借地法は借地人に非常に手厚い保護を与えており、その典型が「建物買取請求権」です。
契約満了で地主が更新を拒んだ場合でも、借地人は建物を時価で買い取るよう請求できる(旧借地法4条2項)ため、借地人の財産的損失を防ぐしくみになっています。
旧法契約が残る主な理由
改正当時の経過措置
新法施行前(1992年8月以前)に契約していた場合、当時の条件を維持することが許容される。
地主・借地人が新法への切り替えに合意しない
双方が再契約を望まなければ、旧法のまま継続されます。
新借地借家法のポイント
新借地借家法は、従来の借地法と借家法を一本化し、平成4年(1992年8月1日)に施行されました。
旧法と同様に借地人の保護は基本に据えられていますが、定期借地権の導入などにより契約形態の選択肢が増えました。
普通借地権と定期借地権
普通借地権
旧来の借地権と同様に更新があり、地主の更新拒絶は正当事由がないと認められない。
最初は30年以上で、初回更新後20年、以降の更新は10年となり堅固建物、非堅固建物などの区別はなくなりました。
定期借地権
更新がなく、契約期間満了で建物を壊して更地にして返すのが原則。
新借地借家法の定期借地権と事業用定期借地権の活用
新借地借家法では、借地契約の期間や更新の有無を柔軟に設計できるようになりました。
| 一般定期借地権 | 契約期間を50年以上(譲渡特約付きの場合は30年)とし、終了後は建物を取り壊して更地で返還。 |
|---|---|
| 事業用定期借地権 | 10年以上50年未満まで設定可能。居住用建物はNG、店舗や事務所など事業用途に限られます。 |
| 建物譲渡特約付借地権 | 最初の契約で建物を地主に譲渡する特約を結ぶことで、契約満了後は建物を相当の対価で買い取ることが義務づけられ、借地人は建物を処分して退去。 |
これらは都市の再開発や事業向け土地活用において、地主にとっては「土地が長期にわたり戻ってこないリスク」を限定しつつ安定収益を得る手段として利用されています。
借地人側から見れば、定期借地なら安価に土地を借り事業をスタートできる利点がある反面、満了時には退去が原則。事業計画と契約期間を明確に織り込む必要があります。
地主との交渉ポイント
増改築時の承諾料
借地上の建物を増改築する際は、地主の承諾が必要なことが多く、その承諾に伴って承諾料が求められるケースがあります。
地代の増減請求
借地借家法には地代の増減に関する規定があり、地主側が相場上昇等を理由に値上げ請求することが可能です。
ただし、地主側にも合理的根拠が必要で、交渉や調停などが行われる場合もあります。
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中
借地権付き物件のメリット・デメリット
| 借地権付き物件のメリットとデメリット | |
|---|---|
| メリット | 土地購入費を抑えられるため、都心など地価の高い地域でも取得しやすい 相続税評価などが所有権より低くなる可能性がある 場合によっては広い敷地をリーズナブルに利用できる |
| デメリット | 地代を長期で払い続ける必要がある 増改築や売却で地主の承諾が不可欠 担保評価が低く、金融機関からのローン審査が厳しい場合がある |
借地権の相続・売却・譲渡におけるポイント
借地権は普通の不動産(所有権)よりも手続きが複雑になりやすいです。
地主との関係が必須であり、法律や慣習が絡むため、専門家を交えたサポートが望ましいケースが多くあります。
相続時の注意点
承諾料の発生する場合がある
借地権自体は当然に相続されます。法廷相続人が相続した場合には名義変更料(譲渡承諾料)は原則かかりません。
しかし、遺言書で〇〇に遺贈すると記載があった場合には承諾料が発生してしまいます。
旧借地法か新借地借家法かの確認
相続を受ける建物が旧借地法契約の場合、今後も旧法ルールが継続しますが、地主も相続時などに契約書を新借地借家法に切り替えようとする可能性もあります。
旧借地法か新借地借家法を確認する場合は、当初の土地賃貸借契約書や地代の領収書などの日付で確認するしかありません。ですので、契約書関係や地代の領収書などは取っておいたほうがいいでしょう。
売却・譲渡時の流れ
地主への相談
借地権を第三者へ譲渡・売却する場合、まず地主の承諾が必要です。無断譲渡は契約違反となる恐れがあるので、事前に了解を得ましょう。
ですが、売却が決まってもいない状況で地主に話してトラブルになるケースもあるので不動産会社に相談してから判断するのがおすすめです。
承諾料の交渉
一般的に借地権価格の10%程度を承諾料とする慣行が多いとされますが、地域性や交渉力によって異なります。
売買契約と名義変更
地主から承諾書を得たら、買主と売買契約を結び、名義変更を行います。地代の支払先も新たな借地人へ切り替わります。
金融機関の融資事情
借地権付き物件は所有権物件より抵当評価が下がりやすく、住宅ローン審査で減額や断られる場合もあります。
ただし、借地権対応ローン商品を扱う金融機関もあり、事前の情報収集が重要です。
トラブル事例と解決の糸口
事例1:地主と地代の大幅値上げでもめる
背景:地代が周辺相場より安いからと地主が一方的に値上げを通知。
解決:借地借家法では、地代の増減請求は公平性に基づき認められますが、請求額が不当に高いときは裁判所に調停を申し立てられます。
専門家の役割:地代に関して法的根拠はないため、一般的に土地(底地)の固定資産税・都市計画税の3~5倍をもとに交渉。
事例2:建物を売却したいが地主が承諾せず
背景:築古の借地物件を売ろうとしたところ、地主が承諾料を高額に設定。
解決:承諾料は地域慣習や裁判例により相場観があります。あまりに高い場合は弁護士等を通じて交渉。
最終的には裁判所に許可を求める方法(借地借家法第19条)もあります。
専門家の役割:価格交渉と法的手続き、地主との関係維持を配慮した折衷案の検討。
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中
借地権の税務・評価
相続税・贈与税
借地権が相続や贈与の対象となるとき、国税庁の定める「財産評価基本通達」に基づき借地権割合をもとに算定されます。
地域ごとに借地権割合は異なり、60%〜90%など大きな幅があります。
土地の評価額×借地権割合で「借地権評価額」が出ます。
地主と借地人が同一人の場合(自地自建)だと借地権は生じない扱いになりますが、実際に複数の相続人間で権利関係が複雑化するケースもあるため、遺産分割協議の段階でしっかり把握することが肝要です。
所得税(譲渡所得)
借地権を譲渡した場合の譲渡所得は、**譲渡収入 −(建物取得費+譲渡費用など)**で計算されます。
譲渡収入の中に承諾料や、地主との交渉費用が含まれるかどうかもポイントです。専門の税理士に依頼したほうが安心でしょう。
よくある質問(Q&A)
Q. 地代を突然大きく値上げされたらどうすれば良いですか?
A. 借地借家法では地代増減請求が認められていますが、地主側にも周辺相場などの合理的理由が必要です。
納得できない場合は交渉・調停・裁判を通じて減額を主張できます。弁護士や不動産鑑定士の協力が解決の糸口となるでしょう。
Q. 地主が変わったら、今までの借地契約は無効になりますか?
A. 土地の所有者が変わっても借地権は継続します。登記などの対抗要件を満たしていれば、新地主に対しても従来の契約を主張できます。
ただし、契約更新や地代の見直しなどで改めて話し合う必要が出てくる場合もあります。
Q. 旧借地法から新借地借家法に強制的に移行させられることはありますか?
A. 基本的にありません。旧借地法当時の契約は経過措置によって旧法のまま継続されるため、地主が一方的に新法に切り替えるのは困難です。
新法への移行は双方合意の上で再契約するかたちになります。
Q. 無断で増改築した場合、どうなるのでしょう?
A. 大幅な増改築を地主に無断で行うと、契約違反とみなされる恐れがあります。
どうしても承諾が得られない場合は、裁判所に「増改築の許可」を申し立てる制度もありますが、まずは協議と専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。
借地権問題は専門家のサポートが解決の近道
借地権問題解決のフロー
- 契約書・地代・地主との関係など現状の把握
- 地主との交渉方針を策定(必要に応じて専門家が同行)
- 増改築、譲渡、建物建替えなどの具体的施策を実施
株式会社ネクスプラスの強み
弊社(株式会社ネクスプラス)は、不動産買取会社として、借地権の買取や権利調整、不動産開発・再生・管理を得意としています。
以下の点で多くのお客様を支援してまいりました。
権利調整ノウハウ
地主と借地人の両者の視点を踏まえ、スムーズな交渉と合意形成をサポート。
不動産買取・再生サポート
借地権付き物件でも積極的に買取し、資金化を後押し。老朽化した建物の再生案や、活用アイデアを提案します。
専門家ネットワーク
税理士・弁護士など各分野のプロとも協力し、相続税対策や契約書のリーガルチェックをトータルにサポート。
専門家に依頼するメリット
迅速かつ正確な法的アドバイス
借地借家関連の法律は細分化されており、旧法・新法・経過措置・地方自治体の条例など、多岐にわたります。
専門家ならそれらを踏まえたアドバイスが可能です。
地主・借地人双方の利益を考慮した交渉
弁護士や不動産会社が間に入ることで、感情的な対立を避け、合意形成をスムーズに進められます。
売買・再開発時のノウハウ
借地権付き建物をどう活用するか、再開発や等価交換などの手段も含めて多角的に検討できます。
借地権をめぐるお悩みは早めの対策がおすすめ
借地権は、法律的に複雑なだけでなく、地主との長期的な関係が不可欠です。
そのため、自己判断で物事を進めるとトラブル化しやすい領域です。
「家族が相続した借地物件を処分したい」「増改築したいが地主との話し合いがうまくいかない」などの具体的な悩みがあれば、不動産専門企業や法律の専門家に相談するのがベストです。
弊社(株式会社ネクスプラス)では、不動産買取会社としての強みを活かし、借地権を含むさまざまな不動産トラブルを解決へと導いています。
相続や買取、再利用のプラン作りなど、ワンストップでお手伝いいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
以上が、借地権に関する包括的な解説と活用法のご案内です。旧借地法・新借地借家法の両面からチェックし、あなたの状況に応じた最適な選択肢を見つけてください。
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中