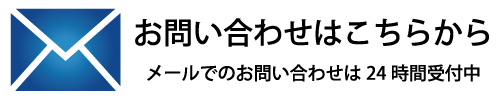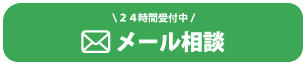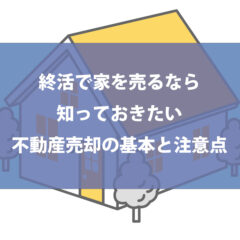敷延土地の売却完全ガイド:売れにくい土地でも損をしないために
敷延土地(敷地延長・鍵型土地)とは?特徴と定義を解説
敷延土地の意味と「敷地延長」との違い
「敷延土地」という用語は、一般にはあまり聞き馴染みがないかもしれませんが、実務的には「敷地延長(しきちえんちょう)」「鍵型土地」「旗竿地(はたざおち)」などとも呼ばれ、同様の概念を指すことが多いです。
たとえば、旗竿地では、別名『敷地延長』や『敷延(しきえん)』とも呼ばれます。
敷地延長とは、道路に接する間口が狭く、その間口から細長い「竿」状の通路を経て奥に「旗」状の敷地があるという形状を指します。
つまり、一般の整形地(たとえば、正方形・長方形で道路に広く面している土地)とは異なり、形状・接道条件・使い勝手の面で制約を受けやすいため、売却時に注意すべきポイントが多く存在します。
「旗竿地」「鍵型土地」とも呼ばれる理由
上述の通り、竿(通路部)+旗(奥の敷地部)という構造が「旗竿(はたざお)」と呼ばれる所以です。これが「敷地延長」という名称で呼ばれる背景には、道路への接道部が延長(細長く)なっているという形状から来ています。
また、「鍵型土地」と言われる場合もありますが、これは土地の形が鍵のような形状(通路部 → 奥の広がり)になるためです。どの呼び方も実質的には「道路から奥まっている」かつ「間口が狭い」土地を指すことが多いと理解しておいて問題ありません。
どんな形の土地が該当するか|図解付きで解説

たとえば、以下のような条件が当てはまると敷延土地と認識されやすいです
- •道路との接面が2m~数mしかない、かつ奥に長い通路がある
- •通路部分は居住空間というより「アクセス用通路」に近く、実際に建物が建つ部分が奥にある
- •土地の上で建物配置・駐車スペース・採光・通風などに制限が生じやすい
建築基準法との関係と制限内容
敷延土地を理解するうえで重要なのが、 建築基準法 における「接道義務」です。一般に住宅用地として建物を建てる場合、幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があるとされています。
しかし、敷延土地の通路部(竿部)がこの条件を満たしていない場合、建築不可または建築制限付きとなる可能性があります。
さらに、地域の条例によって「路地状部分の長さが20mを超えると幅員を3m以上確保せよ」といった追加制限も存在します。
したがって、売却を考える際には、まずこの接道義務の確認、通路部の幅・長さ・道路・私道・公道の区別などを事前に調査することが不可欠です。
道路との接道義務と敷延土地の扱い
接道義務を満たしていない土地(例えば道路との接面が2m未満、通路幅が狭すぎる、私道で通行承諾がない等)は、建て替え・新築ができない「再建築不可物件」と扱われるケースがあります。
このような建築制限がある土地は、買い手にとってリスクが高く評価額が下がる傾向があります。そのため、売却を検討する場合には「接道を満たしているか」「将来建て替えが可能か」といった点を明確にしておくことで、買い手の安心材料となります。
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中
なぜ敷延土地は売れにくい?5つの理由
接道面積の狭さが買い手に不人気
敷延土地では、道路に面している間口が狭い(2~3m程度)という物件が多いです。そのため、車の出入りが難しい、資材搬入が困難、建築費が増えるなどのデメリットがあります。
例えば、「旗竿地・売れない理由」として、「建築費が高くなりがち」という指摘があります。
また、間口の狭さ・通路部の長さがあることで、敷地面積が少ないと判断されがちです。
これは、竿部分は有効宅地面積に算入されないためです。有効宅地面積とは、建築物が立てられる土地の面積を指します。
陽当たり・通風が悪いケースが多い
敷延土地は奥まった位置に建物が来るため、隣家に囲まれて日当たり・通風が確保しづらいというケースがあります。
このような環境的なデメリットは、住まいとして暮らす買い手にとって大きなマイナス要因となるため、売却交渉時に価格を下げざるを得ないこともあります。
建築自由度が低い・再建築不可になる可能性
接道義務を満たしていない通路部を有する敷延土地は、建物の建て替えができない「再建築不可物件」になるケースもあります。
買い手が将来建て替えを検討していた場合には、敬遠される傾向があります。
住宅ローンの審査が厳しくなる場合がある
物件が一般的な整形地と比較して評価が低く、融資が受けにくい傾向にあります。
これにより、買い手が住宅ローンの申請で難航する可能性があると判断されると、購入希望者自体が減少することもあります。
地価評価や査定額が低くなる傾向
敷延土地は、整形地に比べて地価・路線価・実勢価格が低めに設定される傾向があります。
たとえば、「間口が狭く奥行きが長い」などの不整形地補正が必要になるためです。
その結果、「同じエリア・同じ㎡数の整形地と比べて7割~8割くらいの評価額になる」という実例も報告されています。
こうした“値段が下がる”という前提が買い手や売り手双方に影響し、売却まで時間がかかるケースが多くなります。
敷延土地でも高く売却するための5つの戦略
接道部分を整備して見た目と印象を改善
敷延土地では“通路(竿部)”部分がネックになるため、まずこの部分の印象を改善することが有効です。
例えば、通路幅を明確にし、舗装・照明・門扉・植栽などを施して「通路として使いやすい・安全・明るい」という印象を与えることができます。
実際、旗竿地売却ノウハウでは「通路部分を駐車場として活用できるようにする」などの提案があります。
「単なるアクセス用通路」というマイナスの印象を、「有効活用できる通路・駐車スペース付き」というプラスに変えることが可能です。
建築プラン付きで販売する
敷延土地を“土地として売る”だけでなく、「建築可能なプラン付き」「設計付き」「リフォーム済み」の形にして販売することは、買い手のハードルを下げる手段となります。
例えば、既存建物があればそのまま売ることで、解体費用・リスクを買い手が回避できるというメリットがあります。
つまり、建築プランを提示することで「狭くても建てられる・使える土地」という見込みを買い手に示すことが、価格交渉力を高めるポイントとなります。
隣地との共同売却・合筆を検討する
敷延土地では「隣地所有者」との関係も売却を左右する重要な要素です。
隣接する整形地の所有者が、拡張・駐車場・庭を増やしたいと考えているケースもあります。
実際、「前方の整形地の方に購入を打診する」という売却戦略が有効とされています。
また、隣地と合筆して一つの整形地として売り出すことで、形状のマイナスを打ち消すことも可能です。
売却戦略として「隣接地の所有者への打診+合筆検討」は有効な手段となります。
買取業者への直接売却を検討する
敷延土地は一般仲介での売却では時間がかかることが多いため、あらかじめ買取業者を活用して“早期売却”を検討するのも戦略です。いわゆる「不動産会社が直接買い取る」方式です。
「早めに現金化したい」「売却期間を短くしたい」など目的が明確な場合に検討しましょう。
「旗竿地・敷地延長に強い」不動産会社に依頼する
一般的な不動産会社では敷延土地の扱いに慣れていないケースがあります。売却戦略の立案・買い手の探索には専門知識が必要です。
実際、「敷延土地の売却に慣れている不動産会社を選ぶことが重要」との指摘があります。
そのため、「敷地延長・旗竿地実績あり」「変形地の販売に知見あり」という会社を選び、複数社比較(相見積もり)を行うことが望ましいです。
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中
敷延土地の売却価格と相場の見方
査定方法の基本(接道・形状・周辺相場)
敷延土地の査定を行う際、一般的な整形地と比較して「間口狭小補正」「奥行長大補正」「不整形地補正」などが適用されます。
例えば、まず「敷延でない土地としての仮の査定価格」を出し、そのうえで形状等の補正を掛けて実査定を出す流れが紹介されています。
また、近隣の成約事例・路線価・公示地価などを基に比較する「取引事例比較法」や「路線価法」などが使われることがあります。
減価率の目安|通常土地より何%下がる?
実務的には、敷延土地は整形地と比較して 評価額7〜8割程度 にとどまるという実例があります。
例えば、ある記事では「旗竿地の価値は7割~8割くらいの評価額になることが多いです」と記載されています。
ただし、地域・立地・面積・接道状況・用途など条件によってかなり変動しますので、「7〜8割」という数字はあくまで目安です。
固定資産税評価額との関係
敷延土地は評価が低めとなることから、固定資産税評価額も整形地より低くなる傾向があります。
ただし、売却価格=固定資産税評価額ではなく、実勢価格・査定価格・売出価格とそれぞれ異なる評価基準であるため、注意が必要です。
市街地・郊外での相場の違い
敷延土地の売れ行き・評価は、立地によって大きく差があります。
住宅密集地・都市部では敷延土地でも「安価ながら立地条件が良い」ため需要があるケースもあります。
一方で、郊外・地方ではアクセスの問題・通風・日当たり・車利用の制約などが重なり、さらに売れにくい傾向があります。
売却戦略を立てる際には、地域特性を踏まえてどのようなターゲット層を狙うかを検討すると良いでしょう。
敷延土地の売却手順と必要な準備
現地調査と測量
敷延部の長さや幅、接道状況を調べ、現況測量図を用意します。
境界確定と承諾書の取得
通行部分が私道や共有地の場合、通行・掘削に関する承諾書が必要です。
建築可能かの確認
市区町村の建築指導課で建築可否の確認を行い、売却時にその結果を提示できるようにしておきます。
売却先の検討(買取前提)
買取業者へ相談し、現地を見てもらった上で価格提示を受けます。複数社に依頼することもありますが、業者の対応力や実績も重視しましょう。
売買契約と引き渡し
合意に至れば契約書を締結し、必要書類をそろえて引き渡します。
必要書類と事前の調査事項
売却を進めるにあたって、以下のような書類・情報を準備しておくとスムーズです
- •登記事項証明書(所有者・抵当権・地目など)
- •公図・地積測量図(敷地の形状・通路の長さ)
- •接道状況を示す図面・写真
- •建築基準法・条例に関する情報(通路部の幅員、建築不可かどうか)
- •固定資産税評価証明書
- •既存建物がある場合、その状態や築年数・構造など
特に敷延土地では接道義務関連、私道か公道かの確認が売却価格・買い手の安心につながるため、事前の調査が重要です。
測量・境界確定の重要性
通路部が細長かったり、隣地との境界があいまいだったりすると、買い手からの信頼が下がる原因になります。
特に、通路部分が「共有地」や「私道」にあたる場合は通行承諾書の有無、維持管理の条件などが問題になりやすいため注意が必要です。
可能であれば売り出し前に境界確定測量を行い、買い手に安心感を提供できる状態にしておくと良いでしょう。
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中
敷延土地の売却成功・失敗事例から学ぶ
リフォーム+建築プラン付きで高く売れた事例
ある物件では、敷延土地上に既存の住宅があったため解体せず、そのままリフォーム済みとして「中古戸建+敷延土地」として売却したところ、予想より早く買い手がついたという報告があります。
このように、建物付き土地としての販売、特に「すぐ入居可」「リフォーム済み」という条件を付けることで、敷延のデメリットをある程度フォローできます。
売れ残りで価格を下げざるを得なかった失敗例
一方、売却戦略をあまり検討せず、「整形地と同じような価格設定」で売り出してしまったため、販売期間が長引き、やむなく価格を大幅に下げてしまったという例もあります。
実例では「日当たり・通風が悪い」「通路が狭く車が入らない」等の理由で買い手がつかず、価格を下げて対応したという内容があります。
このようなケースから学べるのは、「始めから現実的な価格設定をする」「売れにくい理由を明確にして対策を講じる」ことの重要性です。
相続放棄・売れずに管理コストだけが残ったケース
特に相続などで敷延土地を取得された方の中には、「売ろうと思ったが買い手がつかず、固定資産税・管理費・草刈りなどのコストだけがかかった」というケースも報告されています。
このような事態を防ぐためにも、早めに売却活動を開始するか、売却が難しいと判断した場合は他の活用策を検討すべきです(次章参照)。
売却が難しい場合の代替策
不動産買取業者に即時売却
前述の通り、売却期間を短縮したい・管理コストを早く減らしたい場合は、不動産買取業者への直接売却を検討できます。
ただし、価格は一般売却よりも低くなる傾向があります。
それでも「売れないまま管理費・固定資産税だけがかかる状態」よりは現実的な選択肢となることがあります。
定期借地権や賃貸での運用
買い手がつかない敷延土地であっても、土地活用として賃貸駐車場・倉庫・貸ガレージなど、用途を変えて収益を上げる仕組みを検討することも可能です。
この際には、通路部の利用、アクセス確保、賃料設定、管理体制などを事前に検討しておくことが重要です。
隣地への譲渡・合筆の交渉
敷延土地が単独では売りづらい場合、隣地所有者との協議により「隣地と合筆して一体利用」「隣地所有者に譲渡」などを検討するのも1つの方法です。
前述の売却戦略部分でも紹介しましたが、隣地所有者にとってメリットを提示できればスムーズに交渉が進む可能性があります。
資産活用型(駐車場・倉庫)としての選択肢
敷延土地の通路部・奥まった敷地構造を逆手に取って、「駐車場」「バイク置場」「トランクルーム」「倉庫用地」など、一般の住宅用地とは異なる用途で提案することも有効です。
特に、車の出入りが可能な通路幅(例:3m程度)があれば駐車場用地としての需要があります。
敷延土地売却でよくある質問Q&A
Q. ローンが残っていても売れる?
A. はい、ローンが残っている土地でも売却自体は可能です。ただし、売却価格がローン残高を上回るかどうか、抵当権の抹消や清算の手続きが可能かどうかを事前に確認する必要があります。特に敷延土地では評価が低く出る可能性があるため、「売却価格-ローン残高」を慎重に見積もることが大切です。
Q. 再建築不可物件でも売却可能?
A. 再建築不可となっている敷延土地(接道義務を満たしていないなど)は、売却可能ですが、一般の住宅用途想定の買い手は少なく、価格も下がる傾向があります。
売却成功のためには、用途・買い手ターゲットを変える(例:収益用、駐車場用地等)か、既存建物付き・用途転換型で販売戦略を立てることが重要です。
Q. 建物が古い場合どうすればよい?
A. 古い建物がある敷延土地を売却する場合、「解体して更地にする」「リフォームして中古戸建として売る」「そのまま建物+土地として売る」のいずれかを検討します。
敷延土地では、解体して更地にすると建築制限が明確になり買い手がつきやすくなる反面、解体費用・更地化後の固定資産税増加などがコストになります。
Q. 固定資産税はどうなる?
A. 土地の形状や評価額が変わることで、固定資産税の評価額も変動します。敷延土地では一般に評価・固定資産税ともに整形地より低めになる傾向があります。
ただし、売却時には買い手が固定資産税の負担も含めて検討するため、固定資産税評価証明を用意しておくと安心です。
Q. 売却までの期間は平均どれくらい?
A. 明確な平均値は地域・条件によって大きく異なりますが、敷延土地は「整形地と比べて販売期間が長くなりやすい」という傾向があります。
買い手が限定されるため、売却戦略(価格・条件・広告)が適切でないと長期化する可能性があります。
売却を急ぐ場合は、価格を現実的に設定する/買取業者を利用するなど検討が必要です。
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中
株式会社ネクスプラスの強み|敷延土地の売却も安心サポート
弊社(株式会社ネクスプラス)は、不動産買取・再生・調整を専門とする会社として、「敷延土地(敷地延長・鍵型土地)」のような特殊形状の不動産の売却・活用に多くの実績があります。
以下のような点で、一般の不動産会社では対応が難しい案件も積極的にサポートしております。
権利関係・通路問題の調整ノウハウ
敷延土地では、通路部分の幅員不足や、私道・共有地の通行承諾など、権利関係が複雑な場合があります。
ネクスプラスでは、隣接地所有者との交渉や、通行・掘削承諾書の取得支援など、スムーズな合意形成をサポートいたします。
敷延土地の買取・再生提案が可能
「建物が古い」「建て替えできないかもしれない」「接道が不十分」といった問題がある土地でも、弊社では直接買取を行い、活用・再生の可能性を広げます。
リフォーム提案、建築プラン付き売却など、売却しやすくなるご提案も豊富です。
専門家ネットワークによる万全のサポート
土地活用や相続、売却に関わる法的・税務的な対応も、税理士・司法書士・弁護士などの専門家ネットワークを通じてワンストップでサポート。
安心して手続きを進めていただけます。
専門家に依頼するメリット|敷延土地こそプロの知見が必要です
正確な法的・建築的アドバイス
敷延土地は建築基準法・都市計画法・接道義務など、法規制の影響を大きく受けます。
専門家のアドバイスがあることで「再建築不可リスク」や「用途地域制限」を見落とさず、損をしない判断が可能になります。
感情的トラブルの予防と交渉支援
私道の通行権や隣地との境界交渉など、敷延土地特有の調整は、感情的な対立が生じやすい場面でもあります。
専門家が仲介することで冷静な合意形成が可能になります。
売却だけでなく活用・再開発の選択肢も提案
単に売却するだけでなく、リフォーム、賃貸、合筆、分筆など、敷延土地のポテンシャルを最大限に引き出す選択肢をご提案できます。
建築家や開発会社との連携も可能です。
敷延土地のお悩みは早めの対策を
敷延土地は、「評価が低い」「売れない」とあきらめられがちな不動産ですが、正しく理解し、戦略を立てれば有利に活用・売却することが可能です。
「相続した敷地延長の土地をどうしたらいいかわからない」「建て替えも難しそうで困っている」などの具体的なお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
ネクスプラスでは、不動産買取・再生・権利調整における専門性を活かし、お客様の不安を安心に変えるお手伝いをいたします。
まとめ|敷延土地の売却で損をしないために
知識と戦略次第で「売れない土地」は変わる
敷延土地は確かに「売れにくい」「評価が低くなる」という側面がありますが、それは形状・接道などのネガティブ要因が買い手に伝わってしまった場合です。
逆に、これらの要因を把握・説明・改善し、マイナスを最小化する戦略を立てれば、十分に売却は可能です。
プロの活用で売却成功率が高まる
変形地・敷延土地の売却には、専門知見がある不動産会社の選定、複数社からの査定・提案比較、建築プラン・通路改善・用途転換などの販売戦略が必要です。
「敷延土地に強い」という実績のある会社をパートナーに選びましょう。
早めの行動と情報収集がカギ
売却を先延ばしにしてしまうと、固定資産税・管理費がかかるだけでなく、状況が変わってより売れにくくなるリスクもあります。
まずは査定を依頼し、どの程度の価格が期待できるか、どのような戦略が必要かを早めに把握することが大切です。
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中