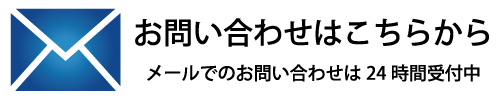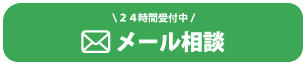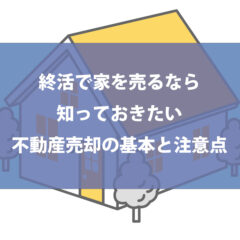【底地と借地権を同時に売却するには?】国有地・財務省のケースで実例解説!
国が所有している底地とは?その正体と背景を解説
日本には、建物の所有者と土地の所有者が異なる「借地権付き不動産」が数多く存在します。特に国(財務省)が所有する「底地」は、歴史的・制度的な背景を持つ特殊な資産です。
このセクションでは、「底地」とは何か、なぜ国が所有しているのか、その仕組みと現状について詳しく解説します。
底地とは?借地権との違いとセットでの解説
「底地(そこち)」とは、建物所有を目的に他人に貸している土地の所有権を指します。一方、借地権とは、その土地を使用する借主側の使用権です。
両者は一つの土地上に共存しており、所有権と使用権が分離された形となっています。
この構造は、法律上「底地権(貸地権)」と「借地権」が並存する二重構造の不動産とされ、一般的な所有権物件とは異なる特徴を持ちます。
| 実務的な違い | ||
|---|---|---|
| 項目 | 底地(地主) | 借地権(借地人) |
| 所有権 | あり(登記あり) | なし(借用権) |
| 利用権 | 原則なし(貸している) | あり(居住・賃貸) |
| 地代収入 | 発生する | 支払義務あり |
| 建物所有 | 不可 | 可能(契約に基づく) |
このように、地主は土地の所有者であるにもかかわらず、使用が制限される一方、借地人は使用権を持ちながら所有権を持たないという相互依存かつ非対称な関係が成り立っています。
なぜ底地と借地権が分かれているのか?歴史的背景
この特殊な権利構造が生まれた背景には、日本の土地制度と住宅政策の歴史的な経緯があります。
| 戦前・戦中期:地主制と借地人制度 | 日本では明治期以降、土地所有権が法的に確立され、大地主が都市部の土地を所有し、多くの庶民が借地人として住宅を建築する形が広まりました。 この時期に制定されたのが、旧借地法(大正10年法律20号)です。この法律は、地主の権利よりも借地人の生活保護を優先する内容であり、借地人が建物を所有し続ける限り契約が継続するという強力な保護制度が導入されました。 |
|---|---|
| 戦後~高度成長期:住宅供給と借地契約の増加 | 第二次世界大戦後の住宅不足に対応するため、国や自治体は不要となった土地(旧軍用地・公共施設跡地など)を民間へ貸与する政策を進めました。その結果、多くの国有地が借地として利用されるようになりました。 こうして「建物は民間所有だが、土地は国のまま」という状態が全国各地で生まれ、現在まで引き継がれているのです。 また、個人・法人保有の底地が相続税の物納として納付される事例は一定数存在し、これを背景に国有となっている底地が見受けられます。 |
底地・借地権付き土地のメリットとデメリット
このような二重構造を持つ不動産には、権利関係・資産評価・活用方法の点で特有の利点と制約があります。
メリット(借地人・地主双方)
- ・借地人は初期コストを抑えて建物所有が可能
- ・地主(底地所有者)は地代収入を得られる
- ・所有と使用が分離されることで柔軟な利用設計が可能
デメリット
- ・所有権が統一されていないため、不動産価値が下がる傾向
- ・借地権者との調整・更新交渉が煩雑
- ・国や公的機関が底地の場合、交渉・承諾取得に時間がかかる
具体例:
- ・「借地権のみ保有していても、建替えや譲渡時に地主の承諾が必要」
- ・「評価額が低く、担保価値が限定されてしまう」
関連記事:借地権とは? 旧借地法と新借地借家法を徹底比較し、相続・売却・地主交渉のポイントまで解説
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中
国が所有する底地の特徴とは?|大蔵省・財務省の底地処分
国が所有する底地には、一般の民間地主とは異なる法律や制度が関わってきます。
特に財務省(旧大蔵省)が管理する「普通財産」に該当する底地は、借地人にとっても取引に関わる不動産会社にとっても、特別な対応が求められる存在です。
このセクションでは、国有底地の制度、管理方針、売却のルールなどを詳しく解説します。
旧大蔵省(現財務省)が所有する底地とは?
かつての大蔵省、現在の財務省は、国が保有する土地・建物を「国有財産」として分類・管理しています。
このうち、「普通財産」と呼ばれるものは、役所や施設などで使われていない、いわば「余剰資産」に該当します。
その中には、以下のような背景で生まれた借地付き底地が含まれます
- ・戦後の復興期に民間へ貸し出された土地
- ・旧軍用地・庁舎跡地などを住宅用地として提供
- ・公共施設が移転・廃止され不要となった敷地
- ・物納などで納められた底地
こうした土地は、建物所有者(借地人)は民間、土地の所有者は国という二重構造になっており、所有と使用が完全に分離された状態です。
国有地(普通財産)の管理体制と処分ルール
国有地のうち、財務省が保有する「普通財産」は、定期的に民間へ売却・貸付されることがあります。
その管理・処分に関する主なルールは以下の通りです。
国の土地を売却する基本ルール
| 処分対象 | 処分方法 | 内容 |
|---|---|---|
| 借地人が買い取る場合 | 随意契約 | 相手が明確なときに限り、契約可 |
| 売却価格 | 鑑定評価 | 不動産鑑定士の評価をもとに決定 |
特に底地を借地人が希望する場合、国は原則として優先的に売却に応じる姿勢を取っており、実際には借地人が底地を取得することで所有権を統一するケースが多く見られます。
財務省が底地を処分する理由と現状の方針
なぜ国が底地を売却するのか、その背景には政策的な目的があります。
主な理由
| 国有財産の有効活用 | 遊休資産を整理し、民間での活用を促進 |
|---|---|
| 管理コストの削減 | 地代徴収・契約更新・苦情対応などの手間を軽減 |
| 地価上昇地域における市場価値の顕在化 | 保有よりも売却によって財政効果が見込める |
| 底地・借地の分離状態が再開発を阻害 | 土地利用の効率化を進めるため、一体処分が望ましい |
処分方針の傾向(令和以降)
- ・借地人からの申し出による「随意契約」が増加
- ・土地の所在自治体からの要望に基づく売却
- ・同一不動産の**底地と借地権をセットで売却(同時処分)**する事例が増加
このように、国は一体化された所有権を形成しやすい環境を整備し、民間流通の円滑化を促進しています。
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中
借地権者の立場と権利を整理する【旧借地法と新借地借家法】
底地と借地権の関係を正しく理解するには、借地人(借地権者)の法的立場と契約の違いを把握することが不可欠です。
とくに「旧借地法(大正10年)」と「新借地借家法(平成4年)」では、借地人の権利や地主との交渉ルールに大きな差があります。
このセクションでは、借地権の法的性質や、国有地に関する実務的な注意点を詳しく解説します。
借地権の種類と法的背景
旧借地法(1921年施行)による借地契約の特徴
- ・借地権の保護が極めて強力
- ・契約期間は初回30年になりますが、更新後の期間が建物の種別で変わります。
堅固建物:30年、非堅固建物:20年です。 - ・更新拒否には正当事由が必要、実質的に半永久契約
- ・建物が存在する限り、地主からの解約は困難
- ・借地権の譲渡や建替えも、比較的自由に可能(承諾料等は別途必要)
現在でも、多くの国有地の借地契約がこの旧借地法に基づいており、借地人の権利が非常に強い構造が維持されています。
新借地借家法(1992年8月1日施行)による借地契約
- ・借地権は「普通借地権」と「定期借地権」に分類
- ・普通借地権:初回30年、更新後20年→以後20年ごとに更新
- ・定期借地権:更新不可・期間満了で契約終了
- ・建替えや譲渡には原則として地主の承諾が必要
- ・借地人と地主のバランスが重視された制度設計
借地人が国有地を借りている場合の立場
国が底地を所有する物件の場合、借地人は原則として民間人または法人です
そして多くのケースでは、旧借地法時代に締結された契約がそのまま自動更新され続けているため、借地人の権利は非常に強固なものとなっています。
実務上の重要ポイント
- ・財務省は借地人の使用実績や契約状況を重視
- ・借地人からの申し出があれば、底地の随意契約による取得も可能
- ・建物の存在・登記の有無・使用実態などが、売却や契約判断に影響
- ・契約書の締結日を見る(1992年8月1日より前か後か)
- ・「定期借地権」と明記されているかを確認
- ・更新条項や借地期間の明記があるかどうか
- ・旧借地法に基づく契約が多く、借地権者が強い権利を持つ
- ・不動産価格の上昇に伴い、所有権統一による資産価値の最大化が求められている
- ・底地の価格:国有地の場合、不動産鑑定士の評価額が基準
- ・借地権価格:地域や契約内容によって異なるが、相場の30~70%程度
- ・建物:築年数・構造に応じて減価償却計算
- ・借地契約の名義・権利関係の確認(相続未登記など注意)
- ・底地・建物の登記簿の照合(所在地・地番が一致しているか)
- ・契約時期と借地法の適用確認(旧法か新法かで権利内容が異なる)
- ・国有地は売却までに3〜6か月程度かかる場合もあり、スケジューリングが重要
つまり、借地人は単に使用者であるだけでなく、交渉の中心的立場を担う当事者であることを理解する必要があります。
契約更新・建替え・譲渡に関するルール
| 項目 | 旧借地法 | 新借地借家法(普通借地権) | 新借地借家法(定期借地権) |
|---|---|---|---|
| 契約更新 | 原則自動更新 (拒否困難) | 正当事由があれば拒否可 | 更新不可 (契約終了で明渡) |
| 建替え | 原則承諾必要 | 原則承諾必要 | 原則不可 |
| 譲渡 | 承諾必要 (承諾料の支払いあり) | 承諾必要 (承諾料の支払いあり) | 承諾必要 (承諾料の支払いあり) |
| 終了時 対応 | 建物がある限り継続 | 建物がある限り継続 | 満了で終了・再契約不可 |
借地権の確認方法と注意点
契約している借地が「旧借地法」「新借地借家法」のどちらに該当するかは、以下の方法で確認できます
不明な場合は、不動産の専門家や、底地買取業者に相談するのが得策です。
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中
底地と借地権を同時に売却する仕組みと流れ
底地と借地権が別々の所有者に分かれている場合、不動産の評価が下がったり、売却が難航したりすることが少なくありません。
こうした状況を解決する手段として近年注目されているのが、「底地と借地権の同時売却」です。
このセクションでは、その仕組みと具体的な流れ、実務上のポイントを解説します。
なぜ同時売却が注目されているのか?
市場のニーズと制度背景
同時売却とは、底地所有者(例:国や地主)と借地人が協議の上、第三者に一括売却する方法です。
買主は土地・建物・借地権すべてを同時に取得し、所有権を一体化できます。
国も推進中
財務省をはじめとした公的機関も、普通財産(土地)の処分において、底地と借地権をセットで譲渡するケースが増加しています。これは、底地だけでは買い手が見つからないことが多いためです。
同時売却の流れ(財務省+借地人+買主)
| 借地人と底地所有者(国や地主)間で売却の意思確認 | 底地:国が所有するケースでは財務省(地方財務局)が対応 借地人:建物所有者としての譲渡意思 |
|---|---|
| 株式会社ネクスプラスによる一括買取提案 | 底地と借地権の同時購入を希望
財務局と随意契約または入札による底地取得 借地人から建物および借地権の譲渡契約を締結 |
| 登記・引き渡し・所有権の統一 | 所有者が一本化され、通常の所有権物件として再流通可能に |
価格設定と実務上の注意点
鑑定評価と価格の決め方
実務上の注意点
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中
同時売却のメリットとデメリット
底地と借地権を一体として売却する「同時売却」は、従来のように権利が分かれたままの状態よりも、取引の自由度や不動産価値の面で多くの利点があります。
ただし、同時売却ならではの注意点も存在するため、メリットとデメリットの両面を正しく理解することが重要です。
このセクションでは、実務的な観点から同時売却の効果を解説します。
同時売却のメリット
- 1. 不動産価値の最大化(所有権の統一)
- ・底地単独:流動性が低く、収益性も限定的
- ・借地権単独:建替え・転売に制約あり
- ・統一後:フルスペックの「所有権物件」として再活用が可能
- 2. 売却手続きが一度で完結
- 3. 相続・資産整理の観点でも有利
- ・借地権や底地は評価額が低くても権利関係が複雑なため、相続時にトラブルの原因となりがち
- ・一体化して売却することで、現金化がスムーズに行え、相続税対策や財産分割も円滑
借地権と底地が別々の所有者にある場合、不動産としての価値は著しく下がります。
これを統一することで、完全所有権として市場に出すことができ、資産価値は一気に上昇します。
同時売却により、複数の契約・登記を同時に行えるため、煩雑な手続きを分割する必要がなくなります。
特に相続や将来の土地利用を見据える場合、一括売却は時間と労力の節約につながります。
同時売却のデメリット・リスク
- 1. 関係者間での合意形成が必須
- ・借地人と底地所有者(国や地主)が売却に合意しなければ、同時売却は成立しない
- ・特に借地人が建物に強い思い入れを持っていたり、相続人が複数いたりすると、意見の調整に時間がかかる
- 2. 価格交渉が複雑になりやすい
- ・底地と借地権それぞれに価格があり、評価の差異や負担割合の調整が必要
- ・特に財務省との取引では、公的評価に基づいた売却価格が設定されるため、柔軟な交渉が難しい
- 3. 時間がかかる場合がある(特に国有地)
- ・財務省への申請・鑑定評価・承認プロセスなど、売却まで3〜6か月程度を要する
国有地(国が底地を所有)の場合、譲渡承諾や同時売却の手続きには相応の時間と労力がかかります。
書類のやり取りだけでも4~5往復に及ぶことが多く、その間に財務省や各地の財務局へ出向く対応も必要になります。
書類に不備があれば差し戻しとなり、再提出でさらに期間が延びる点にも注意が必要です。
同時売却の一般的な流れ(例)
- 1.借地権付き建物の売買契約を締結
- 2.底地の「買受申込書」を国に提出
- 3.国から「買受条件」の通知
- 4.借地人が「買受承認通知」を国に提出
- 5.買受条件確定後、底地の一括決済と借地権の決済を同時に実行
※底地の買受申込から決済完了まで、目安は約3か月。
株式会社ネクスプラスのサポート
株式会社ネクスプラスは、国(財務省・財務局)との調整、必要書類の整備・事前チェック、期限管理、決済スケジュールの統合など、煩雑な交渉・実務を一括で取りまとめます。
想定外の差し戻しや抜け漏れを防ぎ、関係者の合意形成を加速させることで、早期の売却成立を力強くご支援します。
同時売却が特に有効なケースとは?
- ・所有者が高齢で相続前に資産を整理したい場合
- ・相続人間での分割トラブルを未然に防ぎたい場合
- ・建物の老朽化が進み、建替え・解体を検討している場合
- ・近隣の開発や土地需要の高まりが見込まれる場合(タイミング重視)
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中
株式会社ネクスプラスの直接買取実例|国有地の底地と借地権を一括取得
株式会社ネクスプラスは、不動産の「権利調整・再生・買取」に特化した専門企業として、底地と借地権が分離された難解な案件に多数対応してきました。
中でも、国(財務省)が所有する底地と、民間借地人が所有する借地権を同時に買い取る「一括買取」実例は、同社の強みを象徴するものです。
このセクションでは、具体的な実例を交えながら、ネクスプラスがどのように買取を実現しているのかをご紹介します。
国が所有する底地に関する案件の背景
ある案件では、以下のような条件が重なっていました。
- ・土地の所有者は国(財務省)、用途は住宅地
- ・借地人は昭和時代から建物を所有し、旧借地法に基づく契約
- ・建物は老朽化し、相続人による今後の活用意向も不明確
- ・借地契約は更新を繰り返し、解消・売却の機会を探していた
このようなケースは全国的にも珍しくなく、借地人も国も「できれば売却したいが、手続きが複雑」という理由で、長年放置されている事例も見受けられます。
ネクスプラスによる買取交渉と調整内容
株式会社ネクスプラスは、買主として以下のような対応を実施しました。
財務省とのやり取り(底地の取得)
- ・地方財務局へ随意契約による取得希望を申請
- ・鑑定評価の取得、法定手続きの履行、必要書類の整備
- ・契約条件の確定、売払代金の納付、所有権移転登記まで実行
借地人との交渉(借地権の取得)
- ・建物所有者(借地人)との譲渡合意形成
- ・建物の状態や評価を説明、適正価格を提示
- ・借地権付き建物を直接買取し、建物を解体・更地化
結果的に、ネクスプラスが底地・借地権の双方を一体で取得し、完全所有権物件として再流通させることに成功しました。
買取後の再生と活用提案
- ・後は老朽建物を解体し、更地に整備
- ・新たな住宅用地として再販または活用(戸建開発や投資用地)
- ・地域需要に合わせたプランニング(ハウスメーカーとの提携も可)
このように、ネクスプラスは単なる「中継業者」ではなく、直接買主としてスピーディかつ確実に案件を進行できる点が大きな強みです。
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中
ネクスプラスの強み|複雑な底地・借地権も安心サポート
底地と借地権が絡む不動産は、通常の不動産会社では対応が難しいケースが多くあります。
とくに、国有地が関わる案件や旧借地法による借地契約など、制度理解と実務対応の両方が求められる場面では、専門的な知見と実行力を持つ会社が必要です。
株式会社ネクスプラスでは、こうした複雑案件に対応できる独自の体制を整え、売主・借地人・行政との調整をワンストップで行っています。
法務・税務・行政対応を熟知したプロフェッショナル集団
クスプラスの大きな強みは、単なる不動産取引の知識にとどまらず、借地借家法・国有財産法・民法・固定資産税法などの制度を横断的に理解し、実務に反映できる点です。
- ・財務省や地方財務局との交渉経験多数
- ・税務処理や譲渡所得の計算サポートも実施
- ・借地契約書・登記内容の調査・整理・再構成まで対応可能
複数の専門士業(弁護士・税理士・司法書士・土地家屋調査士)との連携により、一つの窓口で総合的な手続きが完了します。
借地人との交渉も自社で直接実施
- ・地主と借地人の関係は、ときに感情的・対立的になることもあります。
- ・ネクスプラスでは、仲介ではなく買主の立場で借地人と誠実な価格交渉を行い、トラブルの予防・早期合意形成を実現しています。
- ・特に「旧借地法による借地権者」への対応経験が豊富で、慎重なコミュニケーションと公平な条件提示を重視しています。
一括買取と再生力がもたらすスピードと安心
- ・通常の不動産会社では「底地だけ買えない」「借地だけでは使えない」などの制約がありますが、ネクスプラスはどちらも直接一括買取できるため、迅速に所有権を統一できます。
- ・その後の建物解体、整地、再販売まで自社で一貫対応し、売主・借地人の不安や手間を最小限に抑えます。
再活用の提案力|売却だけで終わらない支援
- ・買取後は「売って終わり」ではなく、再販先や再開発プランの策定まで対応
- ・ハウスメーカー、投資家、地元企業との連携を活かし、地域にとって有益な活用方法を選定
- ・所有権が統一されたからこそ実現できる「土地の最大活用」をご提案します
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中
専門家に依頼するメリット|底地・借地権こそプロの知見が必要
底地や借地権に関する売却・整理・活用は、一般的な不動産とは異なり、法律・税務・登記・交渉といった複数の専門領域が絡むため、専門家の関与が不可欠です。
特に旧借地法が関係するような案件や国有地の売却では、制度理解と交渉技術の両方が必要になります。このセクションでは、専門家に依頼することで得られる具体的なメリットを、法務・交渉・活用提案の観点からご紹介します。
法務・制度への正確な対応が可能
底地・借地権取引には、以下のような複雑な法的要素が含まれます
- ・借地借家法(旧法・新法)の判断と適用
- ・契約内容・契約書の分析と整理
- ・国有財産法、行政財産の取扱ルール
- ・建築基準法や都市計画法による建築制限
専門家であれば、法的に正確な判断をもとに、適切な対応策を立案し、将来的なトラブルや無効取引を防止できます。
交渉・合意形成における第三者的役割
借地人と地主、または借地人同士の意見が対立することはよくあります。
専門家や専門業者が間に入ることで、冷静かつ客観的な交渉が可能になります。
- ・借地人が納得できる価格・条件の提示
- ・感情的な衝突を回避した調整プロセス
- ・共有者や相続人間の利害整理(例:遺産分割協議)
これにより、関係者の信頼関係を損なうことなく、円滑な売却・取得が実現します。
税務・評価・登記など多分野の手続をワンストップ化
底地と借地権の売却には、以下のような複数手続が関わります
- ・不動産鑑定士による評価
- ・税理士による譲渡所得の試算・確定申告
- ・司法書士による所有権移転・抵当権抹消登記
- ・弁護士による契約書チェック・法的アドバイス
これらを個別に依頼していては時間もコストもかかってしまいます。
ネクスプラスのような専門業者を窓口にすることで、すべての手続きを一本化でき、負担を大幅に削減することができます。
活用提案・出口戦略までトータルで支援
- ・単に売却するだけでなく、リフォーム、賃貸活用、合筆、分筆なども含めた包括的な活用提案が可能
- ・市場動向を把握したうえで、売却時期・価格設定・再販売先の見通しを立てることができる
- ・所有権統一後に新たな建築計画を立てる際も、建築士・開発業者と連携したプロジェクト型のサポートが受けられる
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中
底地・借地権の問題は早期相談がカギ
底地や借地権に関する課題は、「建替えできない」「譲渡できない」「評価がつかない」など、時間が経つほどに複雑化しやすい傾向があります。
とくに旧借地法に基づく契約や国有地が関わるケースでは、当事者だけで解決するのは困難です。問題を放置せず、早期に専門家へ相談することで、円満な解決と有利な資産形成のチャンスをつかむことができます。
放置によるリスク|将来的に売却・活用が難しくなる
底地や借地権の整理がされないまま放置されると、以下のようなリスクが発生します
- ・借地人・底地所有者ともに高齢化し、相続人が増えて利害調整が困難に
- ・借地権者が建物を放置・老朽化し、再建築不可・収益不可の状態に
- ・国有地の場合、売却申請タイミングを逃すと、当分の処分が先延ばしに
- ・資産評価が適正に行えず、相続税や譲渡益課税で不利になる
「まだ早い」と思う段階での相談がベストタイミング
「売るつもりはないけど将来に備えておきたい」
「相続対策として底地を整理しておきたい」
「借地人との関係が良好なうちに権利を明確にしておきたい」
こうしたケースでも、早めにプロへ相談することで、想定外のリスクを回避し、将来の選択肢を広げることができます。
ネクスプラスへの無料相談|不動産権利のかかりつけ医として
株式会社ネクスプラスでは、以下のような内容での無料相談を常時受付中です
- ・国有地(財務省)に関する底地売却サポート
- ・借地人との一括売却交渉支援
- ・老朽建物付き借地の買取・再生プラン提案
- ・相続を見据えた不動産権利整理・評価サポート
「不動産のかかりつけ医」として、複雑な権利関係をスッキリ解決し、資産を有効活用できるよう、ワンストップでのご提案・対応をいたします。
底地・借地権の同時売却に関するよくある質問(Q&A)
Q1. 底地と借地権を同時に売却するメリットは何ですか?
A. 同時に売却することで、不動産としての完全な所有権が第三者に移転できるため、流通性や資産価値が大きく向上します。
借地人と地主の利害調整が済んだ状態で市場に出すことができるため、買主にとっても安心材料となり、売却価格が高くなる傾向があります。
Q2. 底地と借地権の売却は別々でもできますか?
A. はい、可能です。ただし、借地権だけ・底地だけの売却は、対象となる買い手が限られるため、条件交渉が難航することが多いです。
価格も低く抑えられやすくなります。そのため、同時売却の方がスムーズかつ高値で取引できる可能性が高まります。
Q3. 国有地や財務省管理地の借地権でも売却できますか?
A. 国有地に設定された借地権も売却可能です。ただし、国(財務省)との契約が絡むため、譲渡にあたっては事前に承諾申請や使用条件の確認が必要になります。
実際に売却できた事例もあり、手順を理解していれば対応可能です。
Q4. 借地権者と地主が協力しないと売却できませんか?
A. 基本的に、底地と借地を同時に売却するには、両者の協力が不可欠です。
単独での売却も法的には可能ですが、買主側にとってリスクが高く、取引が進みにくいことが多いです。
信頼関係を築いたうえでの調整や、専門会社の仲介が有効です。
Q5. 専門の業者に相談したほうが良いのはなぜですか?
A. 底地・借地の同時売却には、法律、契約、税務、行政手続きなど多くの分野が関わります。
素人判断で進めるとトラブルに発展するリスクが高いため、経験豊富な不動産買取専門会社に早い段階で相談することが成功のカギになります。
まとめ|底地と借地権は、プロの力で“価値ある不動産”に
底地と借地権は、「扱いづらい」「流通しない」と言われがちですが、正しく整理し、一体化することで非常に高い資産価値を生み出せる可能性を秘めています。
そのためには、制度・交渉・手続きに精通した専門家の力が欠かせません。
ぜひ、悩みや不安を抱えたままにせず、ネクスプラスへお気軽にご相談ください。
あなたの不動産が、“価値ある資産”として生まれ変わるお手伝いをいたします。
不動産の相談ならネクスプラス!
どんなお悩みでもお気軽にご相談ください
無料相談受付中